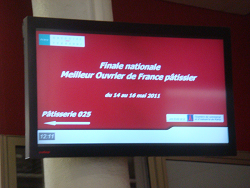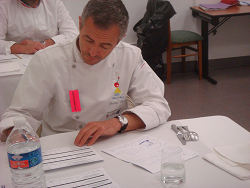|
最終日は、大型工芸菓子と「フランスの伝統的菓子を活かした」組み合わせでの表現。
味覚を大切に、そして「伝統的価値」を育みながら、視覚にうったえるものを・・・
各パティシエも最後の最後まで余念がありません。 |
 |
美味しそうでもあり、美しさも兼ね備えた逸品の数々 |
 |
審査会場に飾られる『味覚と視覚の芸術』 |
 |
審査員であるMOFのみなさんも、最後の最後まで余念がありません |
 |
そして審査発表!
当初発表予定時間を大幅に上回る審査の中、フィリップ・ウラカMOFパティシエ会長から、3名の名前が呼び上げられました
夢に見たMOFのコックコートに袖を通し、感無量の3人。 |
 |
対照的に、惜しくも選からもれたパティシエの方々は何ともいえない「悔しさ」を静かに表現・・・
本学園の講師でもあるMOFニコラ・ブッサン氏(写真右手前)曰く「4年に一度だけあって、4年間あるいはそれ以上の時間を、この数日のために費やしてきたことを考えると、やはり「落胆」は深いものがあります。
であるが故に、我々MOFは選にもれた人たちのメンタル・ケアが重要。
もちろん慰めるだけでなく、何がどうだったかをじっくりわかりやすく説明する『責任』があります。 |
 |
落胆もつかの間、早くも次回に向け、積極的にMOFに声をかけるパティシエ、それに誠実にアドバイスを送るMOF・・・
「紙一重」の数日間をともにした誇り高きパティシエだからこそともにできる時間なんだと思います。 |
 |
一番印象に残ったのは残念ながら選にもれたパパ以上に、号泣しながらパパにしがみついて離れない、小さな子・・・
期間中、当然最終審査会エントリー者とMOF・審査員ごく一部の関係者しか会場には入れないのですが、毎日パパを迎えに来ていた男の子・・・
パパの涙で、思わず号泣していました。
けど、パパは本当に素晴らしかったです!
だれもが、彼にそう語りかけているのが印象的でした。 |
様々なドラマのあったMOF最終審査会視察。
プロとしての「誇り」を大切にした戦いは、また4年後に控えています。
そして、次のドラマはもう始まっています。
今回、非常に貴重な視察をお許し頂いた、フィリップ・ウラカ会長はじめ
関係者の皆様、本当にありがとうございました。











 しているこども達に、興味をもってもらいながら、自分自身を伝えるために、大切なことなのです
しているこども達に、興味をもってもらいながら、自分自身を伝えるために、大切なことなのです

 だからこそ、「季節の先取り」というのが重要な要素
だからこそ、「季節の先取り」というのが重要な要素
 」
」 』と声をかけてくれて、本当に嬉しかったです
』と声をかけてくれて、本当に嬉しかったです